
「記事の書き方がわからない」
「読みやすい記事ってどんな記事?」
「簡単に記事の書き方を知りたい!」
ブログ記事の執筆や、Webライターでの記事の執筆。思っていたよりも難しいと感じている人も多いと思います。
記事の執筆に関しての悩みを抱えていませんか?
そんなあなたのために、記事の書き方をくわしくまとめてみました。
今回の記事では、未経験者、初心者が初めて記事を書く際に注意する点、意識して書くことを中心に記事にまとめていますので、未経験者や初心者レベルの人向けの記事になっています。
この記事でわかることは下記の通りです。
- 初めて記事を書いていく人
- ブログを始めたばかりの人
- これからWebライターとして仕事を始めたい人
には良い参考になる内容になっていますので、ぜひ最後までじっくり読んでくださいね。
- まずユーザーの行動を知ろう
- 記事を書く際に注意したいこと。
- 記事の書き方の基本「PREP法」は初心者には必須!
- 初心者が覚えておきたい記事を書く時の手順4STEP
- 読みやすい記事になっているか不安な時は?
- 見出し(構成)に書く文章の長さの目安
- まとめ:初心者はまずPRIP法を覚えよう!
まずユーザーの行動を知ろう

「ユーザーはどんな風に記事を読むんだろう?」
こんなこと考えたことないですか?
「わかりやすい記事」
「読まれやすい記事」
を考える時は、まず自分がユーザー目線になって考えることが大切です。
ブログ記事など、web上の記事を書くとき、読者は基本流し読みされるのが一般的です。
自分が知りたいことや興味のある内容のみを探すわけですね。
ここではまずユーザーの行動について考えてみましょう。
知りたいことが出てきそうなキーワードで検索する
もし自分が知りたい情報を検索する時ってどうしますか?
例えば、自分のブログ記事をわかりやすく読まれやすいようにしたいなら、
「ブログ記事 読みやすい」
「記事 わかりやすい」
というようなキーワードで検索したりして、調べたりしますよね。
これがキーワードになるわけですが、記事が出てきた時、最短で自分の知りたい情報を見つけたい時に見るのは「目次」です。
そこに自分の知りたいこぐがあれば、ユーザーはそこから飛んでくれるわけです。
だから、キーワードは
記事のタイトルや見出しに入れる
こと。
これが記事をわかりやすくする方法のひとつになります。
記事を流し読みして知りたい情報がありそうならじっくり読む
次に、ユーザーがする行動は知りたい情報があると思われる見出しに飛んだあと、ざっくり記事を飛ばし読みしてからじっくり読むことです。
そこでわかりやすいようにするために必要なことは、
流し読みした時、目に留まるようにすれば、ユーザーは
「知りたい情報がここにある」
とパッと見ただけで判断できるため、記事を読んでくれます。
「本格的にライティングスキルを身につけたい!」
そう感じているあなたは凄いです。
なぜなら、実際に行動に移して自分に投資できる人はホントに一握りで、本気で稼げるようになりたいと考えている人だからです。
webライターやブログで稼いでいる人はホント一握りの人たち。
我輩は、独学でライティングスキルを身につけていったので、めちゃくちゃ遠回りをした人間なので、その分苦労もいっぱいしました。
また、ライティングスキルを身につけても、仕事が受注できなければ収入はゼロです。
そうならないためには、仕事に直結したライティングスクールを選ぶべき。
今なら無料体験レッスンを受付中のスクール。くわしくはこちらをごらんください。
パーソナルWebライティングスクール
記事を書く際に注意したいこと。

まず、記事を書く時に注意したいことを知りましょう。
なぜなら、読みやすい文章を書くためにはユーザーが読みやすいように考えて書く必要があるからです。注意したいことは下記の通りです。
以上4つです。これらの内容を意識して書くことで、読みやすい記事になるんですよ。
順に内容をくわしく説明していきますね。
その1:中学生でもわかる文章を心掛ける
あまり難しい漢字や用語を使わないようにすること。なぜなら、言葉が難しい表現がたくさん出てくると、ストレスを感じることもあるからなんですよ。
どうしても説明や解説を入れると結構使ってしまうことが多くなりますよね。
パソコンで記事作成している方がほとんどだと思いますが、記事作成も慣れてくると漢字変換もスペースキーでポチっとできてしまうので結構スルーされちゃうことが多いです。
漢字については大体の日常的に活用されている漢字は学習できています。
「読むことはできるが書くことはできない」
我輩がそうです(笑)
専門用語
熟語等
を使う際は気をつけたいところですね。
案外できているようで。できていないことがあるので、記事作成したあとの確認の時に文章を見直してみましょう。
その2:ユーザーと同じ言葉遣いを意識する。
ブログ記事だと、意識した方が良いのが「言葉遣い」です。
なぜなら、ブログ記事は専門書や解説記事ではなくもっとラフなイメージがある分、ユーザーは身近な存在であるあなたの記事から知りたい情報がないかを探しに来ているからなんです。
例えば、
「webライターは初心者向けの仕事ですが、実際に稼げている方は少ないです」
「webライターって初心者向けではあるけれど、実際稼げているかはまた別ですよね」
どちらがあなたは親近感わく文章だと感じましたか?
我輩的には後者の方が、親近感があって、読者により近い言葉遣いだと思って例にとして書きました。
誰にあてて書いている文章なのかを考えて、寄り添う感じで書いた方が親近感がわきますよね。
読んでくれる方の目線になって文章を考えて書くようにしましょう。
その3:適度に改行して文章を読みやすくする。
我輩の場合、小説が大の苦手です。
何故なら本いっぱいに文字が並んでいるからです。
もし開けた画面いっぱいに文字が埋め尽くされていたら、せっかく内容の濃い文章であったとしても読みづらくて読むのを諦めてしまいますよね。
適度に改行を入れて空白を入れることで文章は読みやすくなります。
ただ、じゃあ改行する箇所はどこなら良いのか?これには実際に正解はないです。しかし目安ならあります。
文章が切れるところ
ですね。
「、」「。」とかで文章が一旦区切れるところで改行すると良いです。
あまり接続語などを使って1文が長すぎると読みづらさを感じてしまいます。適度に「。」で文章を切っていくと良いでしょう。
その4:適度に「箇条書き」「表」を入れる
これ、めちゃくちゃ大事な要素です。
web上の文章を書く上では基本的に流し読みされることを前提に文章を書かなくてはなりません。
だから、「箇条書き」で文章の要点をまとめることで、
最悪でもその部分に目が留まれば、記事の中で重要なポイントが明確になってわかりやすいことが大切なんです。
また、単に「箇条書き」するのではなく。「枠付き」にするとより引き立たせることができます。
枠付きの箇条書きを書くためには、ちょっとテクニックが必要となります。
「タグ」の知識を必要としますので、知りたい方は一度調べてみてくださいね♪
例えば、はてなブログだと枠付きの箇条書きを入れる場合は、記事の執筆の際に「タグコード」が必要ですし、デザインにもコードを入力する必要があります。
また、表を挿入してわかりやすくまとめることで、読者の目に留まりやすいです。
積極的に使っていくようにしましょう。
その5:トンマナを意識して書く。
次に、記事全体に「統一感」を出すために必要なことがあります。
それが「トンマナ」です。
トンマナとは、「トーン」と「マナー」を合わせた言葉で、あなたが書く記事の全体的な文章の統一感を持たせるためのルールを作ることです。
これが統一されてないと、ユーザーは読みにくさを感じてしまう時があるので意識して書くようにしましょう。
Webライターをやっていると、クライアントによって必ずと言っていいほど作業マニュアルには「トンマナ」の説明書きがありますよ。
それだけ大事なことっていうわけですね。
「トンマナ」についてくわしく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
takumiblog.work
記事の書き方の基本「PREP法」は初心者には必須!
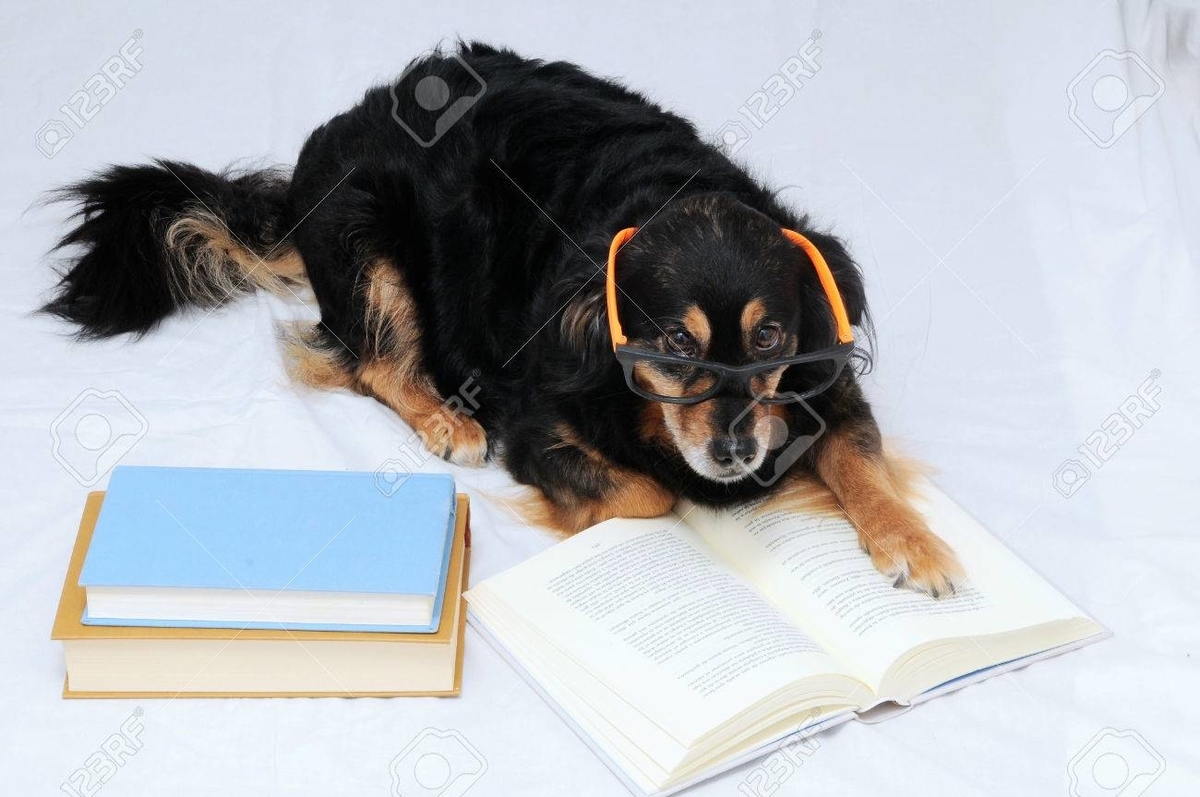
いよいよ記事の書き方の本題です。
記事は「PREP法」で書いた方が良いです。
なぜなら、「ユーザーは結論が早く知りたい」からです。
その結論が読者が知りたい情報であれば記事を読んでくれます。
たとえば、
「webライターにとって必要なものはライティングスキルです。なぜなら・・・」
「webライターにとって必要なものはなんだと思いますか?それは・・・」
という文章では、結果的には同じことを言っていたとしても、わかりやすいのは前者の文章となります。
初めに結論として言っちゃってますからね(^^;)
web上の文章を書くうえで、流し読みされることを前提に考えると、読み進めないと答えがわからない文章では離脱される原因となってしまいます。
そうならないためにも、結論として先に答えを示し、記事に興味をもってもらうことが大切なんですね。
それでは、PREP法についてくわしく解説していきます。
PREP法とは?
PREP法をかみ砕くと以下のようになります。
この順序で文章構成を考えて書くことによって、わかりやすい文章になります。
文章の構成をまとめた代表的なモデルとも言えるでしょう。
内訳はこうです。
「この記事はこんな内容の記事で、こういうことなんです」
と読者に伝えた方が、読者はこの記事はどんなことが書かれているのかを知ることができます。
そして読者の「知りたいこと」を結論として初めに公開しておけば、読者の「読んでみよう」という気持ちを揺さぶることができるわけです。
そのあとにその結論の理由と、具体的な例を書きます。
この「例」を書くこと。
例えば~があれば読者の理解を深められるんです。これ結構大事です。
そして最後にもう一度結論を持ってくること。伝えたいことを繰り返して書くことで、理解を深めることができるからです。
この記事を読んでもらっているとわかると思いますが、簡単にするとこんな感じです。
という風に書けば、一番効率的に文章をまとめることができますよ。
PREP法のメリットとは?
Webライティングでよく利用されるPREP法ですが、ここではメリットについてまとめました。PREP法を用いると、ビジネスのコミュニケーションが円滑になります。
- 「聞き手にストレスをあたえない」
- 「不要なやりとりが減る」
- 「自分の考えを整理する習慣がつく」
というメリットがPREP法にはあります。順に説明していきますね。
〇「聞き手にストレスをあたえない」
PREP法が聞き手にストレスをあたえない理由は、PREP法が先に要点(結論・主張)を伝える構成だからです。先に要点や結論を伝えることによって
「これは何についての話なのか」
を理解した上で話を聞けるため、
「一体なんの話をしてるんだ?」
というストレスが発生しないのです。
〇「不要なやりとりが減る」
PREP法で説明すると、一度の説明で相手に内容を理解していただけるため不要なやりとりを減らすことができます。
逆に、PREP法を意識せずに説明すると、
「ごめん、もう一回説明して?」
「つまりどういうこと?」
「ちゃんとまとめてからもう一度説明してもらえる?」
というやりとりが発生してしまいます。このようなやりとりは小さい時間のロスになり、積み重なれば大きな時間のロスになってしまうのです。しかもこの時間の損失は、話し手だけでなく聞き手にとっても損失ですよね。
ビジネスでは限られた時間の中で成果を出すことが大切です。話し手にとっても聞き手にとっても、不要なやりとりが生まれない説明の構成になっているのがPREP法です。
〇「自分の考えを整理する習慣がつく」
PREP法を心がけて説明するということは、自分の中で
「要点はこうで、理由はこう、理由に説得力を持たせるための根拠は…」
と整理してから説明することに他なりません。PREP法を身に付けられると、報告や説明というアウトプットの機会を通じて、自分の考えを論理的に整理する習慣がつけることができます。
初心者が覚えておきたい記事を書く時の手順4STEP

「記事を書く時の進め方ってあるの?」
どんな風に記事作成に取り掛かればよいのかわからないという方には下記の手順がおすすめです。
上記の4ステップで記事を執筆すると良いです。
まず、書きたいキーワードをリサーチします。リサーチする内容は以下の3つです。
「読者に刺さる文章」
を書くためには、読者のターゲットを絞ることが重要です。なぜなら、ターゲットを絞らないと全て的外れになってしまうからです。
「的は大きい方が良い」
と考えがちですが、実はそうではもないんです。
的が大ききと、かなりの情報量を記事に詰め込まなければなりません。
そうなれば、長文になってしまい、読者が読むのに疲れてしまうんですよね。
リサーチを終えたら、記事の構成について考えていきましょう。
構成を考える時は、初めに持ってくる内容は
「読者が一番に知りたい情報(顕在ニーズ)」
です。読者の早く知りたいに応えるためにも、知りたい情報は先に応えてあげることです。
その次に、
「読者が知ると重宝する情報(潜在ニーズ)」
です。
これは、読者が知りたがっている情報に対して補足となる情報や、一緒に調べている情報なんかを乗せてあげることで、読者の”一石二鳥”感を持たせるためです。
記事の構成が出来上がれば、いよいよ記事の執筆をしていきましょう。
この記事で取り上げた「記事を作成するためのコツ」を意識しながら文章を考えて書いていくと良いですよ。
最後は必ず自分の書いた記事を読み返して、確認することを忘れずに。
「誤字・脱字はないか」
「読みにくい文章・表現はないか」
を確認するのはもちろんですが、他の強豪サイトや検索上位の記事内容と被ってしまっていると、”コピペ記事”として認識されてしまう恐れがあります。
ツールを使用するなどしてチェックするのも忘れないようにしましょう。
「コピペチェックツール」
に関しては、詳しい別記事がありますのでこちらをごらんください。
takumiblog.work
読みやすい記事になっているか不安な時は?

「自分の書いている記事に不安がある」
初心者には必ず付きまとうことだと思います。
そんな時、誰か実績のある人に添削してもらえたら、自分の直すところも明確にできて、ライティングスキルも格段に上がりますよね。
仕事が受注できなければ収入はゼロです。
そうならないためには、仕事に直結したライティングスクールを選ぶべき。
今なら無料体験レッスンを受付中のスクール。くわしくはこちらをごらんください。
パーソナルWebライティングスクール
見出し(構成)に書く文章の長さの目安

一つの見出しの内容説明が長すぎるとユーザーは読むのを辞めてしまいます。
「文章が長いと疲れる」
我輩は、できるだけ簡素に要件をまとめて400文字程度にまとめるようにしています。
その400文字の中でも「PREP法」で文章を作ること。
長くなりそうなら「結論」「理由」「具体例」のみでかまいません。
最後に結論をもう一度言わずとも、先に結論を書いているので問題ありません。
強調したい時は、最後にもう一度「結論」を持ってくるように意識していれば大丈夫です。

